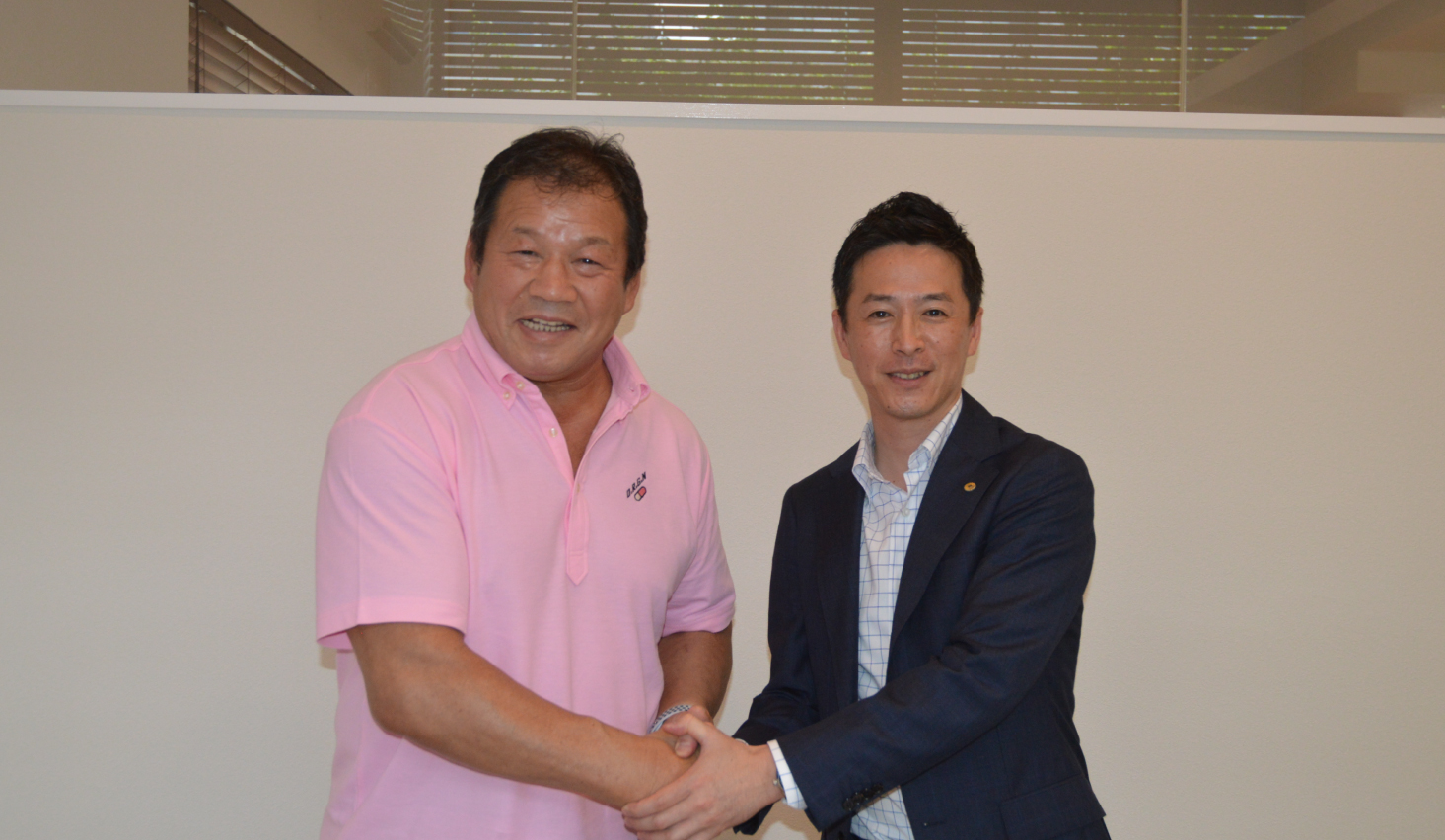2020.07.22
組織の「存在意義」をデザインする。
弊所も2016年に法人に組織変更してから、5期目を迎えています。
毎年毎年、新しい取り組みにチャレンジし、試行錯誤しながら組織作りに励んできました。
「社労士事務所だからちゃんとしてるでしょう??」と、思われるかもしれません。
いえいえ、労務管理は問題ないにしても、組織作りはまったく別の課題です。
組織マネジメントの理論はわかっていても、実践は別物です。
数年前までは5,6人の個人事務所でしたが、現在は14名(社労士5名、有資格者1名、その他メンバー)の、ちょっとした組織に成長しました。
当時10名程度の規模になったころから、メンバー一人ひとりとの接点の機会や関係性の持ち方などについて考えるようになり、「どうしたらチームワークを発揮する組織にできるだろうか?」という大きなテーマがふわーっと降りてきました。
部下が10名くらいになると、一人では見れなくなってくるのと同じですね。
自分もプレーヤーですし。
もしかしたら似たようなことに直面している企業も多いのではないでしょうか。
「これくらいの規模になってきたときに組織作りに取り組む企業は成長しますよ~!」と常に経営者に助言している身ですが、身をもってその難しさを実感してきました。
私がこれまで特に意識して取り組んできたことを振り返ってみると…
- 経営者としての覚悟を決める。
- 社員一人ひとりを家族だと思って付き合う。
- 組織の習慣を作り上げる。(風土醸成)⇒これがたくさん!
- 仕事への追求と執着(大事なこだわり)
- 新しいことへのチャレンジの連続
- 組織の「存在意義」(ミッション、ビジョン、バリュー)をみんなで分かち合う。
それなりに、やってきた自負はあります。
新型コロナウイルス感染症の拡大を機に、世の中の価値観までも大きく変化してきているまさに、先が見えない時代。
私たちのような中小零細企業は、何をよりどころに経営をしていけばよいのでしょうか? どうしたら、人やリソースが集まる組織になるのでしょうか?
経営者の悩みは尽きないですが、その答えを導くための一つの問いが、
「私たちは、何のために、ここで、ともに、働いているのか?」
という問いだと思います。
まさに、この会社の、この組織の、「存在目的」「存在意義」「存在価値」を問う問いです。
その問いに対して、経営者が自分の言葉で語れないのであれば、社員もおそらく同じです。
社員一人一人が自分の言葉で語れるような組織にしていきたい。
そんな、「小さくとも強い組織」を目指して、先の見えない未来を語るのが、
経営者の役割だと強く思います。
立派な言葉でなくてもいい。等身大の自分たちを語れる組織にしていきたい。
はい、目下、取組中!!です。(笑)